クロスインデックス現地調査員による新興国19カ国レポート 第69弾 – 中国 2012年04月10日
- ホーム
- >
- 現地ビジネスレポート
- >
- クロスインデックス現地調査員による新興国19カ国レポート 第69弾 – 中国 2012年04月10日
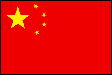
クロスインデックス現地調査員による新興国19カ国レポート
第69弾 – 中国 2012年04月10日
新興国19カ国レポートについて
海外調査や海外進出、海外出張などを検討しておられる企業の方々を対象に、クロスインデックスの現地調査員からの情報を元に掲載しております。
BRICs、NEXT11、VISTAなどのキーワードで取り上げられ、注目されている新興国のうち、韓国、中国、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、マレーシア、インド、バングラデッシュ、パキスタン、ロシア、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、UAE、エジプト、トルコ、南アフリカ、ナイジェリアなどの国々を対象としております。(国別レポート一覧はこちら)
| ←68弾 トルコ | 第70弾 トルコ→ |
中国の自動車産業拡大への日本企業の参画
|
中国の自動車産業発展の歴史を少し紐解いて見よう。1970年代は文化大革命の名残が色濃く残っていた時代であり、国内の全ての産業が「自力更生」の御旗の元、計画経済体制を支える歯車として存在し、自動車製造企業も、国から与えられる生産台数のノルマを達成するだけの役割を果たせば良い国営企業であった。 生産された車両は全て国家が全国に分配。性能、価格、数量など全ての面において最終ユーザーの意向は殆ど無視、文句があるなら供給しない。こんな風潮の下で、長春解放号(4トン ガソリンエンジン トラック)、湖北 東風号(4トン)、南京躍進号(2トン)、北京ジープ、上海乗用車工場、以上5社にて総生産台数が僅かに20万台に満たない状況であった。 |
巨大な市場への取り組み
|
|
|
80年代に入り、中国は重要な生産財としてのトラック生産の技術改革、生産台数拡大の為に、主管部門である第一機械工業部(経済産業省に当たる)は、全世界に向けて「先進的技術導入による、100万台生産体制の確立」に対する協力を呼びかけ、全世界の有数な自動車企業が前述の5大自動車工場を訪問し工場技術改造策を論じたが、具体化することができなかった。 一大転機は、1985年ドイツVWが世界で初めて上海乗用車製造廠と合弁でサンタナを製造するという、当時の常識では考えも及ばない決断を下した時からである。 この間には日本の自動車産業も様々な中国側の要求に応えて、中国各地の工場を訪問、中国の自動車産業の発展に寄与すべく、又将来の巨大な市場を見据えて取り組んできたが、その大きな流れに乗ることは叶わなかった。日本自動車産業各社が中国に最後の参入のチャンスを得たのは1990年代の後半~2000年代の初頭に掛けてであったが、西独VWやAUDI のようなポジションを勝ち得るには至らなかった。 |
|
|
|
共同での技術開発もう現状では日本の自動車産業にとって、中国では世界が注目するプロジェクトの可能性は全くないのであろうか? 一つだけ残されていると思う。即ち中国がこれまで国の威信を掛けて再開発を目論見、結局未だに実現していない「紅旗号」である。長春でAUDIの生産が始まった折、AUDIをベースにした新型紅旗号のプロトタイプは出来たが、あくまでAUDIのノック・ダウン生産を流用したに過ぎない製品であり、他の自動車工場も世界から導入した新型車種を大量に生産し、国産化を進めてはいるが、未だにどの工場も独力で新車を開発できる技術力が備わってはいない。 日本企業がその技術開発力を提供することによって、中国が世界に胸を張って送り出せる政府公用車としての紅旗号の共同開発の道こそ、現在の中国の自動車産業界における日本企業の面目躍如のプロジェクトになるであろう。 |
| ←68弾 トルコ | 第70弾 トルコ→ |
- サービス
- 海外コンサル・海外調査
- 翻訳関連
- 通訳等派遣関連
- 外国人人材紹介 派遣関連
- 編集関連
- 主な実績
- 主な取引先
- よくある質問
- 海外トピックス
- お客様の声
- 国際ビジネス便利ツール
- マーケティング用語集
- ビジネスに役立つ速記法
- ショートカットキー一覧
| ガバレッジ国 | 141 ヶ国 |
|---|---|
| エキスパート国籍 | 138 ヶ国 |
| 対応言語 | 340 言語 |
| エキスパート | 14,369 名 |
| 海外提携企業 | 421 社 |



